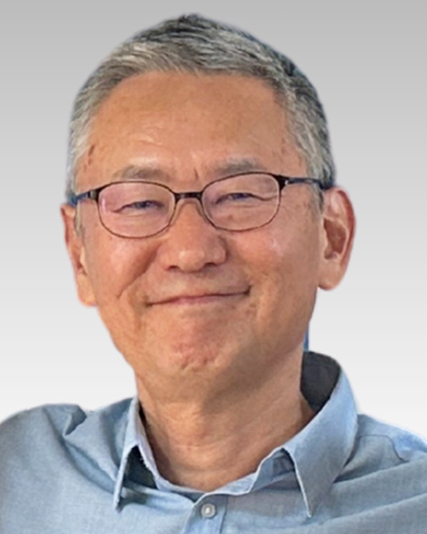
特定非営利活動法人アムダ 理事長 佐藤 拓史
1965年生まれ
岡山県立岡山大安寺高校を卒業
東京大学卒業後、浜松医科大学を経て、アフガニスタン難民医療支援活動、スーダン(内視鏡支援活動)、カンボジア医療支援など救急医療、国内外の災害医療に携わる。2015年よりAMDAの人道支援活動に参加。2023年12月より特定非営利活動法人アムダ理事長に就任。
〈これまでに参加した主な活動〉
| 2015年 | ネパール地震被災者緊急医療支援活動 |
| 2016年 | 熊本地震緊急医療支援活動 |
| 2016年 | ハイチハリケーン後のコレラ感染拡大に対する支援活動 |
| 2017年 |
AMDAネパールダマック病院 、モンゴル国立医科大学で 内視鏡技術移転、 モンゴル・ウランバートル救急サービスで救命救急の講義と実践実施。 以降、モンゴル国立医科大学では招聘教授として毎年プロジェクトを実施 (コロナ渦の2年間を除く) |
| 2020年 | 熊本県球磨地方被災者緊急支援活動 |
| 2022年 | ウクライナ避難者支援活動 |
| 2024年 | 令和6年能登半島地震被災者緊急支援活動 |
- 2019年 モンゴル保健大臣より名誉勲章を授与
- 2025年 モンゴル国立医科大学客員教授に就任
平素よりAMDAに対し格別なご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
私は岡山で生まれ育ち、岡山大安寺高校で学びました。当時は、アフリカでも東南アジアでも中東でも戦争が絶えることなく、世界では毎日多くの人々が犠牲になって命を落としていました。食べることすら難しい国々では、毎日栄養失調で亡くなっていく子供達が絶えません。本当なのか?どうして貧困はなくならないのか?高校生の頃、不思議で仕方ありませんでした。大学生になった頃から、世界で何が起こっているのか自分の目で見て知りたくて、世界中を旅することを始めました。自分で行動してみないと何も納得できないと思っていたからです。たくさんの国を旅して必死に生きる人々の現実を知り、自分に何かできることがあるのか、医師になった今でも考え続けています。
AMDAでは、これまで国内外の災害医療支援、海外への日本の医療技術移転に携わってきました。背景の異なる人たちと一緒に時間を共有することで深く理解し合い、初めて自分のできることが見えてきます。誰かが困っていたら、国籍や宗教の違いなど関係なく、自分のできることをするのは当たり前だと思っています。医師としてやることも、全く同じです。できることがある、それは嬉しいことです。
菅波先生の築き上げたAMDAが、世界の大きな変化の中でも普遍的な意義を持ち続け、未来に継続していくこと。そのための役割を担うことが、自分の天命かと考えています。まだまだ未熟ですが、いろいろな方々のご協力を賜りながら、少しずつでもお役に立てればと思っております。
前任者と変わらぬご支援ご高配を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

ネパール地震被災者緊急医療支援活動

熊本地震緊急医療支援活動

ハイチ ハリケーン後のコレラ感染症拡大に対する支援活動

ウクライナ避難者緊急支援活動

モンゴル内視鏡技術移転事業

令和6年能登半島地震被災者緊急支援活動
【TEDx TALKs】

特定非営利活動法人アムダ 副理事長 難波 妙
2003年よりアムダに勤務。広報室、アムダインターナショナル部門の連絡調整業務、2008年11月より代表部参事、2011年7月より理事、2023年12月より特定非営利活動法人アムダ 副理事長に就任。
〈これまでに参加した主な活動〉
| 2004年 | スマトラ島沖地震支援活動 |
| 2010年 | ハイチ大地震支援活動 |
| 2011年 | 東日本大震災緊急支援活動 |
| 2016年 | 熊本地震被災者緊急支援活動 |
| 2018年 | 西日本豪雨災害被災者緊急支援活動 |
| 2022年 | ウクライナ避難者支援活動 |
| 2024年 | 令和6年能登半島地震被災者緊急支援活動 |
| 2025年 | モンゴル内視鏡技術協力事業 |
緊急医療支援活動時のAMDA多国籍医師団派遣の全体調整を担当。その他にも海外への内視鏡等の医療技術移転事業など、アムダ インターナショナル事業全般にわたって担当し、主に事業対象国の政府、保健省、大学関係者、日本国内では政府関係、駐日大使関係との折衝業務に携わっている。
AMDAは2024年に創立40周年を迎え、これまで69カ国で249件に及ぶ緊急医療支援を行ってまいりました。私がAMDAで活動を始めたのは2003年。当時、前理事長・菅波茂の「相互扶助を世界の共通語にしたい」という言葉が強く印象に残っています。支援活動を通して多くの苦難と向き合う中、困っている人を助けたいという想いが人々を動かし、支援の輪が国境や文化を越えて広がっていく様子を、私は何度も目の当たりにしました。
また、かつて支援を受けた人が今度は支援する側として立ち上がる「恩送り」の連鎖や、医学生として研修に参加した若者が医師としてAMDAに戻ってくる場面に立ち会うたび、人道支援の力と尊さを実感しています。
現代は、デジタル化による便利さの反面、人と人とのつながりが希薄になりがちな時代です。だからこそ、直接心に届く「相互扶助」の精神が、今あらためて重要だと感じています。2023年に就任した佐藤拓史新理事長のもと、“チームAMDA”の一員として、これまで支えてくださった皆さまへの感謝とともに、次世代にこの理念を受け継いでまいります。

東日本大震災緊急支援活動

熊本地震被災者緊急支援活動

西日本豪雨災害被災者緊急支援活動

ウクライナ避難者支援活動

令和6年能登半島地震被災者緊急支援活動

モンゴル内視鏡技術協力事業
理事紹介(五十音順)
-
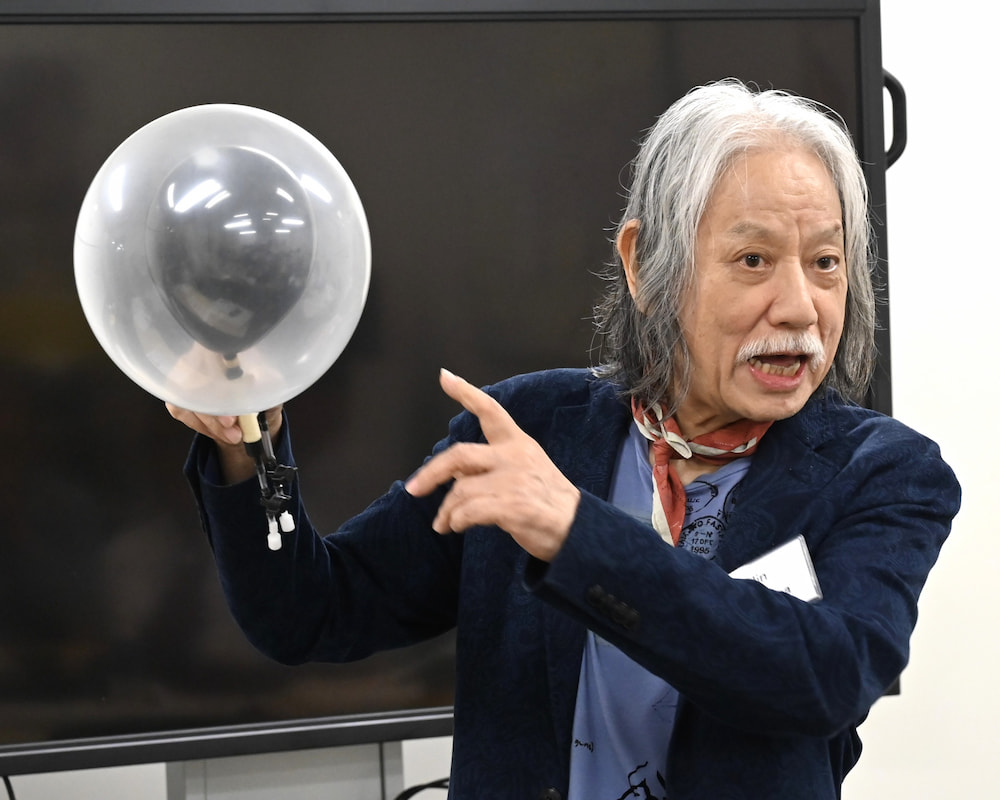
数学者 秋山 仁
人生の師 秋山仁先生
秋山先生は世界的数学者として様々な数学の未解決問題を解き明かし、また教育現場では長年にわたり各界の人材育成に貢献されてきました。
自分の人生を切り開く力を身につける、そして自分が心から楽しいと思えることを全力で続けていく、これは秋山先生から学んだ私の原点です。
個性を貫く生き方の中には、思いやりの心と、自分と異質な他人を認められる寛容な心が重要であると学びました。
AMDAの重要な役割である次世代の人材育成において、秋山先生が実践されてきた生きる力を養う教育は幸せな未来を開く鍵になると確信しています。(AMDA理事長 佐藤拓史)
-

第6代 岡山県立大学 学長 沖 陽子
岡山県立大学第6代学長の沖陽子先生は、農学・環境学、とくに雑草学の分野で高く評価される研究者であり、長年にわたり教育・研究に尽力されてきました。
AMDAは2010年に岡山県立大学と包括連携協定を締結し、2013年には総社市を加えた「世界の命を救う三者連携協定」を締結。災害医療や人道支援、地域づくりの分野での協働を深めてきました。沖先生は学長として、この協定に基づく連携の実践的展開を支え、AMDAの知見を取り入れた「災害医療援助論」などの授業を通じて、学生が国内外の災害医療・支援活動を学ぶ環境づくりに尽力され、教育・研究と現場をつなぐ役割を果たされました。そして現在、AMDA理事に就任された沖先生には、今後さらに災害医療・人材育成分野での多大なご支援ご指導を頂けることを心より期待しています。(プロジェクトオフィサー アルチャナ ジョシ)
-

岡山大学教授 頼藤 貴志(疫学・衛生学分野)
頼藤医師は、長年にわたりAMDAの活動に深く関わってきました。そのきっかけは、大学5年時に参加したAMSA(アジア医学生連絡協議会、1980年に菅波代表らが設立)の会議でした。2007年のAMDA Internationalインド会議以降、2016年熊本地震、2020年熊本球磨地方豪雨災害、2024年能登半島地震など、数々の緊急医療支援の最前線に立ってきました。また、2016年から19年まで毎年、夏にアフリカのルワンダに赴き、現地の医療者や教育関係者とともに児童の健診を行い、学校健診の重要性を伝えてきました。現在もルワンダの若き医療者とともに、地域、保護者、教育の現場が一体となって子どもの健康を見守る学校保健の推進に尽力しています。
大学時代に頼藤医師は、出身地の熊本県八代市近くで発生した水俣病を目の当たりにしたことがきっかけとなり、病気の広がりや原因を解明する学問である疫学を専門としています。現在も毎月水俣へ通い、水俣病患者の診察を続けています。また、岡山県感染症対策委員会委員として新型コロナウイルス感染症対策に深く携わり、岡山県クラスター対策班の事務局長を務めています。 頼藤医師の豊富な知識と鋭い洞察力が、AMDAの災害支援活動の現場でも活かされています。
頼藤医師のように、公衆衛生医師として、地域の健康課題に取り組み、社会に貢献したいとお考えの方はこちら をご参照ください。(AMDA副理事長 難波妙)





