AMDAが生まれて今年で35年。その間、そして、それ以前の学生組織の時代から、私たちを支えていただいた方々がいる。このシリーズでは、こうした皆さんの声に耳を傾けながら、AMDAの「これまで」と「これから」を考えたい。
最初に登場いただくのは藤原健さん。古希を前にしても、現役の新聞記者であり、沖縄の近現代史研究者でもある(略歴は後述)。藤原さんのジャーナリストとしての生き方を3回に分けて連載する。第1回目は「夢の同志」。菅波代表との出会について紹介する。
夢の同志
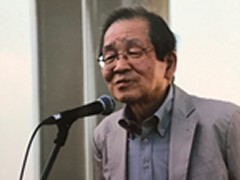
何ともよく似た感性を沖縄で感じた。AMDAの菅波茂代表がもう一人、沖縄にいた。錯覚である。しかし、その放つエネルギーから、そんな感じを受けたのだ。
ジャーナリスト、藤原健さん。「戦に与しない。弱い立場に追いやられている人の側に立つ」と言い切るさまは、人間味あふれた視点と相まって「人間ジャーナリスト」とでもいうべき造語でしか形容できない何かに満ちていた。それは、菅波代表が「相互扶助」をキーワードにアジア・アフリカを語るときのそれに酷似している。

藤原さんは毎日新聞などの仕事を全うした後、3年前に移り住んだ沖縄でがんに冒された。胃を全摘手術し、転移が判明したため退院後も抗がん治療を続けながら、このほど『魂(マブイ)の新聞 「沖縄戦新聞」沖縄戦の記憶と継承ジャーナリズム』(琉球新報社刊)を上梓した。その「出版記念感謝の集い」が過日、那覇市内で開かれ、菅波代表は以下のメッセージを寄せた。
少し長いが、2人の関係がよくわかるので、そのまま引用する。 
藤原健さんは「信念の人」「行動の人」「執念の人」です。
1970年代、藤原さんは支局の駆け出し記者時代からからインドシナ難民に関心を寄せ、AMDAがまだ学生組織だった「西日本医学生連絡協議会」のメンバーと共にタイ・カンボジア国境に足を運んで難民に対する救援のあり方を長期連載で明らかにしました。
私は当時、その学生らを医局の駆け出し医師の立場から束ねていました。そのときからの40年のお付き合いです。
冒頭に示した藤原さんの人柄は、この間の私たちの活動にさまざまな形で関与してくださった姿を通して私が常に感じてきたものです。
私たちはアジア、アフリカ、中南米の計32カ国に支部を持ち、「救えるいのちがあればどこまでも」をスローガンにしています。海外の戦災地、自然災害の被災地での緊急医療救援だけでなく、阪神大震災、東日本大震災など国内の被災地でも活動し、近年は 南海トラフの大地震を想定した医療救援ネットワークの構築を進めています。
こうした活動を評価していただき、沖縄県から2004年、第2回沖縄平和賞を受けました。

ブトワール母と子の病院
その前、1995年10月には、毎日新聞から第7回毎日国際交流賞を受けています。
この年の1月に、阪神大震災が発生し、6400人以上の命が失われました。私たちもすぐに医療支援活動を始めました。その救援メンバーにネパールからの留学生が加わっており、「私たちの国の乳児の死亡率は非常に高いのに、首都のカトマンズ以外には乳児専門病院がありません」という声を、当時、社会部デスクだった藤原さんは聞き漏らしませんでした。そして驚いたことに、すぐに特派員をネパールに派遣し、「震災救援のお返しに、ネパールに子ども病院を」のキャンペーンを始めたのです。
「明日を生きたい」という、日本の被災地とネパールの窮状の両方を見据えて藤原さんがタイトルを命名した連載の指揮を執ったほか、社会部デスクから被災地の阪神支局長に転じた後も、私とともに自らネパールに飛んで病院用地の取得など、立ち上げの最初から尽力されました。世界的に名高い建築家、安藤忠雄さん設計のその病院はお釈迦様の生誕地に近い都市、ブトワール市にあり、今、年間出産数6000件、2012年には日本の外務省からの支援で周産期病棟もできました。
私たちの活動に絡んで、「本業」の記者としても活躍する姿も見ました。
医療活動を通じて海外の要人が交流を求めて、AMDA本部のある岡山にやって来ることがありました。アフガニスタンのタリバンの閣僚、タイの軍事政権に抵抗したチャムロン氏など、メディアが注目する人物には、必ず藤原さんが単独インタビューをねらい、ことごとく成功していました。大阪から岡山までの新幹線の中や、国際会議の時間をぬって他社を出し抜くその行動力と記者としてのセンスには、毎回、感心させられました。
沖縄で沖縄戦や沖縄ジャーナリズムの研究活動を始められたとお聞きしたときからは、平和に関係した仕事に没頭されていることに間違いないと確信していました。
私たちAMDAの平和の定義は「今日の家族の生活と明日の希望が実現できる状況」です。今日の生活とは、食べることができて健康であること。明日の希望とは子どもの教育です。これを阻害する要因が、紛争、災害、貧困です。人種や宗教、歴史など多様なアジア・アフリカで活動しながら、平和構築のための「相互扶助」を前提にしたパートナーシップがどれだけ大切かということを実感しています。
あらためまして藤原さん、出版おめでとうございます。
専門分野に違いはありますが、藤原さんは沖縄で、私が今感じていることと同様の想いの中にいらっしゃるはずで、私の永遠の同志であります。
健康を回復され、今後もご活躍されることを心から祈念しています。
藤原さんを必要とする人たちがまだまだ、何人もいます。
2019年8月5日 活動先のクアランプールより、菅波茂
1946年、広島で生まれた菅波代表と、1950年、岡山県で生まれた藤原さん。「畑違い」の2人の交流は40年以上前にさかのぼる。
菅波代表はインターン、藤原さんは支局に赴任してそれほど年月は経っていない。2人ともいわば、「駆け出し」だった。ただ、まだ何事も成し遂げていなかった2人に共通する夢があった。それは、「助け合う人々」であり、その結果としての「平和」であった。それぞれに、出会った「1枚の写真」がその夢を支えていた。
菅波代表は17歳の頃に出会った『記録写真 太平洋戦争史』の中に掲載されていた写真に目をとめた。若き日本兵が海岸の浅瀬で横向きに死んでいる写真。顔は半分、砂浜に埋っていた。自分とそう年の変わらないと思われる当時の彼がなぜこのような場所で、このような死を迎えたのか、その心の動きが、争いのない人間社会を目指すAMDA創設のきっかけとなった。
藤原さんも同様に高校時代に運命を変える1枚の写真に出会っている。ベトナム戦争中に撮られた写真「安全への逃避」。戦火から逃れるために母親が小さな子どもを抱えながら対岸から川を懸命に渡ってくる写真。この写真は1966年にピュリッツァー賞を獲得している。その後、毎日新聞の記者となった藤原さんは20年後のベトナム取材でその写真の子どもたちを執念で探し出している。通訳と監視を兼ねて藤原さんのそばにいつもいたベトナム関係者は「そんな無理なこと」と冷ややかだったが、藤原さんには不思議な、しかし、強い自信があった。「この子たちは生きている。必ず、会える」。私にはこの経験が今の藤原さんの生きざまに繋がっているように思えてくる。
2人を遥かなる夢へ誘ったのは、ともに「戦争」だった。それが、「戦争を起こさせないための行動や言論」に移っていく。
2人はほとんど同じ言葉で、相手を描き、自らに重なる。「夢を持てばそれが実現すると強く思い込む。国境、差別、制度、壁の克服にたじろぐより前に、夢がある。必ず夢は実現できるというゆるぎない信念を持つ」。それぞれ医師として、ジャーナリストとして専門は異なっていても、DNAの二重螺旋構造のように時には交わり、そして離れてまた交わりながらそれぞれの人道支援活動に携わることになる。
藤原 健(ふじわら けん)略歴
1950年、岡山県生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒。毎日新聞入社。阪神支局長、大阪本社社会部長、同編集局長などを歴任。スポーツニッポン新聞社常務取締役を退任後の2016年に入学した沖縄大学大学院現代沖縄研究科沖縄・東アジア地域研究専攻修士課程を18年修了。同年12月、『魂の新聞』を出版。19年3月、『魂の新聞』で現代沖縄研究奨励賞を受賞。現在、琉球新報客員編集委員として大型コラム「おきなわ巡考記」や沖縄戦関連の書評を執筆。沖縄大学地域研究所特別研究員。
共著書に『沖縄 戦争マラリア事件 南の島の強制疎開』、『介助犬シンシア』、『対人地雷 カンボジア』、『カンボジア 子どもたちとつくる未来』など。
95年の阪神大震災をきっかけにAMDAと連携してネパール子ども病院設立キャンペーンを展開。実現にこぎつけた。98年以降、介助犬の認知キャンペーンを始め、500回を超える連載、テレビドラマ化、兵庫県宝塚市と共催で毎年、シンポジウムを開いて啓発活動を展開するなどして身障者の社会参加を促す「身体障害者補助犬法」制定に尽力した。06年、毎日新聞の「戦後60年報道」で「平和・共同ジャーナリスト基金大賞」を代表受賞。





