
1年の中でも特に「平和」について考えることが多くなるのが、6月23日の沖縄慰霊の日から8月15日の終戦の日にかけてではないでしょうか? AMDAでは、皆さまからいただいたご寄付を「平和」を実現するために行うプロジェクトにも活用しています。
AMDAで言う「平和」とは、「家族の今日の生活と明日の希望を実現できる状況」と定義しています。今日の生活とは、家族が食べられと健康であること、明日の希望とは、子供たちが教育を受けることができ、次世代に繋がっていくことです。その「平和」を阻害する要因が大きく分けて3つあり、1.戦争・紛争、2.貧困、3.災害です。今日は、1.戦争・紛争が起こらないように、取り組んでいるスリランカ和平構築プログラムについてご紹介したいと思います。
スリランカでは、人口の約8割を占めるシンハラ人と約2割を占めるタミル人が対立し26年に渡る内戦が勃発しました。直接的な紛争の引き金は、ほとんどがシンハラ人で構成される政府によるタミル語公用使用禁止をはじめとするタミル人排斥政策の施行開始でした。2003年から2005年、2006年の停戦を挟み、最終的に内戦が終結したのは2009年でした。その停戦中に、AMDAはスリランカに医療従事者を派遣し、対立していたシンハラ人、タミル人が住むそれぞれの地域で平等に医療支援活動として巡回診療と健康教育を行う和平構築プログラムを開始しました。「平和」の一部である「今日の生活を実現できる状況」に不可欠な医療を通じて、それぞれの地域で信頼関係を築き、普段、交流することのなかったシンハラ、タミルコミュニティに健康新聞を配布。その新聞は健康に関する情報をシンハラ語、タミル語、英語で発信することに加え、AMDAが活動する地域や学校の代表者からのメッセージも記載していました。このメッセージには、それぞれの地域の状況、AMDAの活動について紹介されており、間接的な情報共有の場にもなっていました。
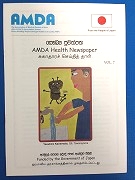

内戦が終結したスリランカにおいて、次世代に「平和」を継承していくために始まったのが、現在も継続して行っているスリランカ和平構築プログラム青少年交流事業です。宗教、民族も異なるスリランカの高校生が通常3日間寝食を共にし、宗教、スポーツ、文化、ワークショップでの活動を通じて交流するプログラムで、今年で6年目を迎えました。全活動を終えた生徒たちは連絡先を交換し、別れを惜しみながら帰途につきます。
言語、宗教、民族が違う青少年たちがスポーツ、宗教施設訪問、掃除、何気ない会話、食事などを通じて交流している様子を目の当たりにして私は、「ここで本当に紛争があったのだろうか?」と思いました。シンハラ語もタミル語もわかりませんが、参加した青少年が違和感なく交流し、別れ際に抱き合い、涙を見せる様子を見たときに、このプログラムの偉大さを肌で感じました。参加した生徒さんたちが、将来、何かあって民族間に不和が生じた際には、この交流の貴重な体験を思い出し、平和のために動いてくれると信じています。


さて、日本においても次世代に「平和」を継承していくというのは大きな課題だと思います。戦争経験者が高齢になる中で、戦争を経験していない私たちがどう「平和」の大切さを学ぶのか。今回、スリランカ和平構築プログラム青少年交流事業にはAMDA中学高校生会に所属する2名の生徒さんが引率の先生と自費で参加し、スリランカの歴史、文化に加え「平和」の大切さも実感したのではないでしょうか。新たな「平和学習」のかたちです。このような草の根の取り組みをこつこつ積み重ねることで、「平和」を次世代に引き継いでいく手助けになればと思います。
AMDAならびに和平構築プログラムに対する皆さまの温かいご理解、ご協力をいただきましてありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。





